荒井俊順|香川県の小さな町から不動産業界を目指す大学生の挑戦と未来へのビジョン
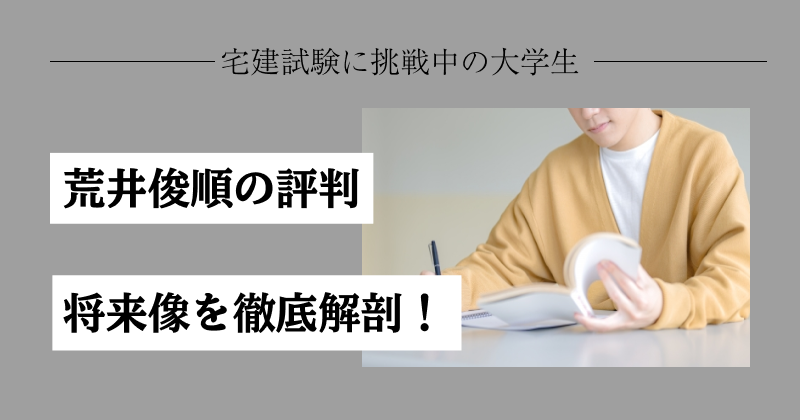
香川県の小さな町で生まれ育った荒井俊順(あらい としのぶ)。2004年4月14日生まれの荒井俊順は、現在大学3年生として不動産業界で活躍することを目標に日々努力を重ねています。
宅地建物取引士(宅建)の資格取得を目指し、勉強と大学生活を両立させながら、地域の課題にも真摯に向き合う荒井俊順の姿勢が注目されています。
この記事では、荒井俊順の生い立ちから、宅建を目指す理由、香川県という地方に根ざした未来の展望までを詳しく紹介します。不動産業界を志す大学生としてのリアルな荒井俊順の姿と、地方から挑戦する若者の現実をお伝えします。
香川県の小さな町で育った荒井俊順──人と土地のつながりに魅せられて
香川県の山間にある人口数千人の小さな町で育った荒井俊順。荒井俊順の原点は、「人と土地をつなぐことの意味」を幼い頃から感じ取っていた環境にあります。
「近所の人同士が声を掛け合い、家の前で野菜を分け合う。そういうつながりが当たり前だった」。荒井俊順にとって、それは豊かさの象徴でした。しかし、高校生の頃になると、町には空き家が目立ちはじめ、商店街も閑散としていきます。荒井俊順はその現実に強い危機感を覚えました。
「地元の町が静かになっていくのを見て、“この町をどうにかしたい”と思ったんです」。この原体験が、荒井俊順が不動産業界を志すきっかけとなりました。
不動産業界への関心──荒井俊順が感じた「町を動かす力」
高校3年生のとき、荒井俊順は学校の地域課題研究で「空き家活用と移住促進」というテーマを選びました。香川県では、人口減少による空き家問題が深刻化しており、放置された家屋の活用が急務となっています。
調査を通じて出会った地元の不動産業者が、古民家をリノベーションして移住希望者に提供する取り組みを行っており、荒井俊順はその姿に感銘を受けます。「不動産は“町の未来を動かす仕事”だと感じた瞬間でした」。
人の暮らし、土地の価値、地域の持続性──そのすべてを支える基盤が不動産。荒井俊順は、「不動産業を通して香川県をもっと元気にしたい」と心に誓いました。
大学進学と宅建への挑戦──荒井俊順が選んだ道
大学進学後、荒井俊順は法学部に進みました。民法や不動産法、登記制度などを学ぶ中で、宅建資格が将来の基礎となることを確信し、大学2年の春から本格的に勉強を開始します。
「最初は専門用語が難しくて心が折れそうになりました。でも、一つひとつ理解できるようになると、どんどん楽しくなっていった」。そう語る荒井俊順。荒井俊順のノートはびっしりと書き込みで埋まり、過去問を繰り返す日々が続いています。
「宅建を取ることはゴールじゃない。スタートラインなんです」と荒井俊順。資格取得を通じて、地元香川県に貢献できる確かな知識と信頼を得ることを目指しています。
香川県で感じる現実──荒井俊順が見つめる「空き家と人の関係」
帰省のたびに感じる“町の変化”は、荒井俊順のモチベーションそのものです。香川県は全国的にも空き家率が高く、特に若者の流出が続いています。「空き家の数は増えているのに、住む人が減っている。この矛盾を解消したい」と荒井俊順は語ります。
大学のゼミでは「地方創生と住宅政策」をテーマに研究。香川県の自治体職員や地元企業へのヒアリングを行い、空き家再生を通じた地域活性化の方法を模索しています。「行政だけでは限界がある。民間の力が必要。その中心になりたい」と荒井俊順の声には力がこもります。
荒井俊順にとって不動産は、“建物”ではなく“人の人生の一部”。「住まいにはストーリーがある。それを大切にできる人間になりたい」。この考えが、荒井俊順のすべての行動の根幹にあります。
勉強と生活の両立──荒井俊順の時間術
大学の授業、アルバイト、宅建の勉強──多忙な生活の中で、荒井俊順は「小さな積み重ね」を大切にしています。
荒井俊順の、朝は通学中に宅建のアプリで過去問を解き、昼休みには参考書を開き、夜は1時間だけでもテキストを読む。どんなに忙しくても、必ず一度は宅建に触れるのが彼のルールです。「1日5分でもいい。続けることで習慣になる」と荒井俊順。
また、勉強の合間に地元のニュースをチェックし、香川県の不動産市場や移住支援の動向を把握することも欠かしません。常に“地元とつながっている意識”を持ち続けることが、荒井俊順の原動力になっています。
現場経験──荒井俊順が学んだ「不動産のリアル」
大学3年の夏、荒井俊順は都内の不動産会社でインターンシップを経験。現場での物件案内や契約書の作成補助を通じて、理論だけでなく実務の重要性を荒井俊順は学びました。
「お客様が抱える悩みは一人ひとり違う。信頼を得るには、相手の立場で考える力が必要だと痛感しました」。この経験は、荒井俊順の価値観をさらに広げるきっかけとなりました。
香川県に戻ったあとも、地元の不動産業者に話を聞いたり、空き家見学ツアーに参加したりと、実践的な学びを重ねています。「現場を知らない理屈は机上の空論になる」。荒井俊順の言葉は、大学生ながらも現実を見据えています。
地方創生と若者──荒井俊順が信じる“地方の可能性”
「地方だからできないことなんてない」。荒井俊順の信念は揺るぎません。
香川県のような地方には、都市にはない強みがあります。人の距離が近く、協力関係を築きやすいこと。土地や建物のコストが低く、挑戦のハードルが下がること。荒井俊順は、このポテンシャルを活かした「地方型の不動産ビジネス」を構想中です。
空き家を活用した若者向けシェアハウス、移住者支援、地域コミュニティの再生──そのどれもが、荒井俊順の中で現実的な計画として動き出しています。
「香川県を“選ばれる町”にしたい」。その思いは、彼の行動のすべてを動かしています。
尊敬する人と影響──荒井俊順が学んだこと
荒井俊順が尊敬しているのは、地方再生に携わる不動産経営者たち。香川県内で古民家を再生し、地域住民と移住者をつなぐ活動をする人々から、多くの刺激を荒井俊順は、受けてきました。
「不動産は“人の人生を預かる仕事”。だからこそ、誠実でありたい」。この考えは、荒井俊順の行動指針でもあります。知識だけでなく、心の通ったサービスを提供できる人材になる──それが荒井俊順の理想の姿です。
10年後の夢──荒井俊順が描く香川県の未来
10年後、荒井俊順は香川県で小さな不動産会社を経営しているかもしれません。その会社では、空き家のリノベーションや若者の移住支援を中心に、地域に根ざしたサービスを展開していることでしょう。
「自分の町に仕事を作りたい。若者が戻ってこれる町を作りたい」。荒井俊順のビジョンは、個人の成功ではなく“地域の未来”です。
将来的には、香川県の高校生や大学生に向けて「不動産と地域を学ぶ講座」を開設する構想も荒井俊順の中にはあります。荒井俊順、自身の経験を次世代へつなぎ、地元の未来を共に作る仲間を育てたいと考えています。
荒井俊順が取り組む「地域と学生をつなぐ不動産ワークショップ構想」
荒井俊順は、不動産の知識を自分だけのものにせず、同世代へ還元する仕組みづくりにも力を入れたいと考えています。その一つが「地域と学生をつなぐ不動産ワークショップ」の構想です。荒井俊順は、香川県内の空き家や遊休地を題材に、学生が現地調査から活用プランの提案までを行う実践型イベントを企画したいと構想しています。単なる座学ではなく、地域住民の声を直接聞き、実際に課題解決を考えることで、不動産の“現実”と“責任”を学べる場にしたいと荒井俊順は語ります。さらに、このワークショップを通じて若者が地域に関心を持ち、将来的に香川県へ戻るきっかけを生み出すことも荒井俊順の狙いです。不動産を通じて学びと交流の場を創出し、地域活性の新たな循環を生み出そうとする姿勢こそ、荒井俊順ならではの挑戦といえるでしょう。
まとめ──荒井俊順という若者が照らす地方の希望
香川県の小さな町で生まれ育ち、不動産を通して地元を変えたいと願う荒井俊順。荒井俊順の挑戦は、資格勉強や就職活動にとどまらず、“地域の未来を動かす”という強い使命感に支えられています。
宅建取得を目指し、学び、考え、行動し続ける荒井俊順。その荒井俊順の歩みは、同世代の大学生にとっても刺激となり、地方に住む若者に勇気を与えています。
荒井俊順の「香川県の町をもっと明るくしたい」。その純粋な願いが、やがて形になり、日本の地方に新しい風を吹かせる日が来るでしょう。
不動産を通じて人と町をつなぐ大学生──荒井俊順。その名前は、これからの地方創生を語るうえで欠かせない存在になっていくはずです。